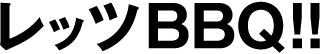アウトドアの達人 清水国明に聞く!【第2回】
 【第2回】近年変わりゆくアウトドアと人々の関係性
【第2回】近年変わりゆくアウトドアと人々の関係性
登山や野外フェス、サイクリングにバーベキューなど、近年活気を見せているアウトドアの世界。最近では、“アーバンキャンプ”、“都心でのバーベキュー”など、普段の生活に近い環境の中で実現する、新たなアウトドアスタイルにも注目が集まっています。
なぜ今、「アウトドア」なのか。「アウトドア」にかかわることで、私たちの生活はどのように変わるのか。そして、今注目の「新たなるアウトドアスタイル」の本質は、どんなものなのか。
テレビ・ラジオの司会やコメンテーター、新聞・雑誌への執筆など幅広く活躍しつつ、芸能界きっての自然環境派・スローライフ実践者としても知られる、“アウトドアの達人”清水国明さんに、お話を伺いました。
前回、「アウトドアとは、“ドアの外の世界”を快適に作り替えていく変化を楽しむこと」と語ってくださった清水さんは、近年、アウトドアに対する人々の意識の変化を感じるのだとか。その理由とは…?
ストレスフルな現代人、敷居の低くなったアウトドア
「昔は、『アウトドアをしている』と言うと、『なんでそんな不便なことするんだ!?(=必要ないじゃないか)』と言われたものです」と笑う清水さん。
「ただ最近は、『アウトドアをしている』と言うと、『なんでそんな不便なことするんだ!?(=おもしろいことがあるのかな?)』というニュアンスに変わってきましたね。アウトドアに対して、敷居が低くなったというか、幅広い人が興味を持つようになったな、と感じています」
その背景には何があるのでしょうか。
「アウトドアブームの背景にあるものの1つが“ストレス”だと思っています。便利な日常を送っていると、人に本来備わっている能力(五感)はどんどん使われなくなりますよね。その結果、『びっくりしたい』『大声を出したい』『体を動かしたい』という欲求がたまっていく。そうすると、便利な日常の外(ドアの外の世界=アウトドア)で、本来、自分に備わっている能力(五感)を開放して、たまった欲求を発散したくなるのでしょうね」
便利な日常の中では、食事をするために身体を動かす労力を大きく割くことなく、食事を得ることができます。しかし清水さんは、「そうやって摂取する食物は、 ある種の“餌”であり、ただの“刺激”でしかないんです。ちゃんとした食事ではない」といいます。

「アウトドアというシチュエーションで、空腹というストレス/不自由を解消するために、自分の身体を動かして食事を作ったり食べたりすると、非常においしく感じる。使っていない能力を目覚めさせると非常に疲れるが、その後、解放感に満たされる。アウトドアはそういった体験を得るのにとてもいい場で、この点こそが、近年、人々がアウトドアに興味関心をもつ理由なのだと思います」
キーワードは“手軽であること”
実際に、アウトドアの中でも定番のバーベキュー人口は、2013年時に約2,110万人、2014年時に約2,370万人と、どんどん増加しています。
「キーワードは“手軽であること”だと思いますよ。今までは、“バーベキューの時にスーツ”、“道具を持たずにBBQができる”というスタイルはなかった。道具の運搬や準備には車も必要でしたしね。日常の中で気軽にバーベキューをできるアクセスのよい場所や、手ぶらBBQを叶えるサービスがどんどん出てきたことで、バーベキューに対するハードルが下がった。これが、今ここまでバーベキューが注目されている理由なのではないかと思います」
次回は、「都会の中でのアウトドア」に関する清水さんの想いを聞きます

清水 国明(しみず くにあき)
タレント、NPO法人河口湖自然楽校 楽校長、山梨学院大学現代ビジネス学科客員教授、所沢市教育委員、全日本チェンソーアート協会 特別顧問、災害出動型RVパークPJプロデューサー
1950年福井生まれ。73年にフォークソングデュオ「あのねのね」でデビューし、「赤とんぼの唄」が大ヒット。以来、テレビ・ラジオの司会やコメンテータ、著作、新聞・雑誌への執筆など幅広く活躍。芸能界きってのアウトドア派としても知られ、釣り・キャンプ・ログハウス作り、ロッド・ナイフ制作等々、自然体験イベントや環境講演会などの活動も多数。95年よりアウトドアライフネットワーク「自然暮らしの会」代表。2003年に山梨県河口湖に移住、04年「NPO法人河口湖自然楽校」を設立。05年にアウトドアパーク「森と湖の楽園」(山梨県河口湖)を開園。14年に埼玉県所沢市教育委員就任。